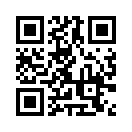2016年04月21日
4/20『第15期ビジネススクール鳳雛塾 1回目』
昨夜から第15期ビジネススクール鳳雛塾をスタートしました。
全5回シリーズの初日スタートです。
今回のテーマは『問題解決・業務改善の基礎』
社内での人間関係の問題解決を飲み会という手法で解決しようとしたケースをもとに
・問題解決が困難な3つの原因
・問題の種類
・問題解決のプロセス
について学んでいきました。

問題は悪魔のスパイラルから深みにはまり
悪魔のスパイラルから脱却できないのは「多忙」と「変化への抵抗」
それを天使のスパイラルに変換するためには「前向きな課題取り組み」が必要
トヨタの「改善」は必要な改善の何%行われているのか
など・・・・

ビジネスシーンのみならず日常の生活の中で誰しもが直面する身近な問題解決につながる内容でした。
いつもながら秋満先生の講座は受講者を魅了します。
この現場にいないと味わえないビジネススクールでした。
これから6月まであと4回実施します。
今後の予定は
5/18(水)論理的思考・ビジネスモデル(「QBハウス」)
6/3(金) ビジネスプロセスと管理(某社の目標管理制度の現状)
6/18(土) 事業主体のあり方(良い会社とは~悩める就活生~)
6/29(水)危機管理・成長戦略(アイドルグループ人気メンバーMの決断)
ご興味のある方は
NPO鳳雛塾 0952-28-8959 までお問い合わせください。

全5回シリーズの初日スタートです。
今回のテーマは『問題解決・業務改善の基礎』
社内での人間関係の問題解決を飲み会という手法で解決しようとしたケースをもとに
・問題解決が困難な3つの原因
・問題の種類
・問題解決のプロセス
について学んでいきました。

問題は悪魔のスパイラルから深みにはまり
悪魔のスパイラルから脱却できないのは「多忙」と「変化への抵抗」
それを天使のスパイラルに変換するためには「前向きな課題取り組み」が必要
トヨタの「改善」は必要な改善の何%行われているのか
など・・・・

ビジネスシーンのみならず日常の生活の中で誰しもが直面する身近な問題解決につながる内容でした。
いつもながら秋満先生の講座は受講者を魅了します。
この現場にいないと味わえないビジネススクールでした。
これから6月まであと4回実施します。
今後の予定は
5/18(水)論理的思考・ビジネスモデル(「QBハウス」)
6/3(金) ビジネスプロセスと管理(某社の目標管理制度の現状)
6/18(土) 事業主体のあり方(良い会社とは~悩める就活生~)
6/29(水)危機管理・成長戦略(アイドルグループ人気メンバーMの決断)
ご興味のある方は
NPO鳳雛塾 0952-28-8959 までお問い合わせください。

2013年03月22日
第12回ビジネススクール(スターバックスコーヒー)
昨夜は、第14期ビジネススクール鳳雛塾の最終回(第12回)を
実施しました。
昨年の6月に開講し、あっという間に最終回を迎えたという感が
あり、受講生の皆さんからもっとケース授業で学びたいという声が
たくさん聞かれました。事務局としても大変有難いことであり、
来年度の15期開催に向けて準備に取り掛かる予定です。


最終回のケースは「スターバックスコーヒージャパン」。
今では佐賀にも店舗があり、身近なコーヒーショップとしてほと
んどの方が利用されているようですが、会社設立の経緯や企業理念、
業績や人材育成制度など、細かいことについては知らないというの
が実情ではないでしょうか。
今回のケースは、2001年、同社がナスダック・ジャパン市場に
上場した頃からの話であり、今後の成長戦略について重要な意思決定
が迫られた時代のものです。
最初にスタバとドトールコーヒーの違いについての議論で盛り上が
り、どっち派か?で熱いバトルが繰り返されました。
直営店方式で出店攻勢をかけるスタバかFC展開で店舗網を拡大し
ているドトールか。
1杯250円(当時)のスタバのコーヒーか、180円のドトール
コーヒーか。
長時間居座ることのできるスタバか、回転率の早いドトールか。
などなど・・・。
両者の財務諸表などを比較検討しながら、それぞれの強みや弱みなど
について分析を重ねていきました。


またスタバの特徴ともいえる「ミッション宣言」「ピープル・ビジネス」
「パートナー制」「スターチーム」「ラーニング」「コーヒー・アンバ
サダー・カップ」「スナップ・ショット」「コンピテンシー評価」など
独特でユニークな制度について、検討を重ねました。
最終的にスタバの成功要因は?、参加した塾生と講師の梁井先生が導い
たものは・・・。
最後のケースに相応しい議論の応酬がなされ、聞き応えのある最終回と
なりました。
参加頂き熱心な議論やケースリードをして頂いた塾生の皆さん、講師の
梁井先生に感謝いたします。
実施しました。
昨年の6月に開講し、あっという間に最終回を迎えたという感が
あり、受講生の皆さんからもっとケース授業で学びたいという声が
たくさん聞かれました。事務局としても大変有難いことであり、
来年度の15期開催に向けて準備に取り掛かる予定です。


最終回のケースは「スターバックスコーヒージャパン」。
今では佐賀にも店舗があり、身近なコーヒーショップとしてほと
んどの方が利用されているようですが、会社設立の経緯や企業理念、
業績や人材育成制度など、細かいことについては知らないというの
が実情ではないでしょうか。
今回のケースは、2001年、同社がナスダック・ジャパン市場に
上場した頃からの話であり、今後の成長戦略について重要な意思決定
が迫られた時代のものです。
最初にスタバとドトールコーヒーの違いについての議論で盛り上が
り、どっち派か?で熱いバトルが繰り返されました。
直営店方式で出店攻勢をかけるスタバかFC展開で店舗網を拡大し
ているドトールか。
1杯250円(当時)のスタバのコーヒーか、180円のドトール
コーヒーか。
長時間居座ることのできるスタバか、回転率の早いドトールか。
などなど・・・。
両者の財務諸表などを比較検討しながら、それぞれの強みや弱みなど
について分析を重ねていきました。


またスタバの特徴ともいえる「ミッション宣言」「ピープル・ビジネス」
「パートナー制」「スターチーム」「ラーニング」「コーヒー・アンバ
サダー・カップ」「スナップ・ショット」「コンピテンシー評価」など
独特でユニークな制度について、検討を重ねました。
最終的にスタバの成功要因は?、参加した塾生と講師の梁井先生が導い
たものは・・・。
最後のケースに相応しい議論の応酬がなされ、聞き応えのある最終回と
なりました。
参加頂き熱心な議論やケースリードをして頂いた塾生の皆さん、講師の
梁井先生に感謝いたします。
2013年02月26日
第11回ビジネススクール(アスクル株式会社)
本日は先程までビジネススクールを開催していました。
今日のケースは、オフィス通販事業を手掛けているアスクル株式会社
のケース。
文房具メーカーのプラス株式会社がアスクル事業を分社化し、オフィス
向け通信販売事業の今後の展開に向けて、重要な意思決定を迫られて
いる時代(1990年代後半)のケースでした。
文房具業界ではガリバー的存在のコクヨ(系列販社を傘下に圧倒的な
シェアを有する)に対抗する戦略として、通信販売事業を核に展開して
いこうとするアスクルがどのような手法を取るべきか?
同業他社が手をつけきれていない30人未満のオフィス市場を主なター
ゲットとして設定し、既存の小売店(文房具店)との共存共栄を保つ
流通チャネルの構築や価格設定等、その戦略について議論していきま
した。


ターゲットとしているオフィスの社員が上司から文房具の購入を依頼
されたシーンを想定した場合、どのような消費行動をとるのか。どこの
お店に買いに行くのか、文具だけでなくどのような関連商品まで購入
するのか、などなどを考えながら、通販という形態でのメリット、デメ
リット等も議論していきました。
最終的な論点としては、当時、圧倒的な在庫量や価格攻勢で日本市場に
参入を予定していたカテゴリーキラーと呼ばれるアメリカの「オフィス・
デポ」や「オフィス・マックス」に対抗するにはどのような戦略を取る
べきか、当時の岩田社長の意思決定(3つの案)について議論を進めま
した。
現在、文具関係のカテゴリーキラーが成功を遂げているかを見てみると
結果は明らかですが、当時の判断は非常に難しかったように思えます。
特に玩具業界のカテゴリーキラーである「トイザラス」は現在の日本で
大成功を収めていることを考えると、玩具と文具の違いは何なのか・・・。
塾生間のディスカッションやケースリード役の講師の私見などから導き
出された見解は実に聞き応えのある内容でした。
参加された塾生はいつもより少なかったのですが、非常に内容の濃い
勉強会になりました。

ご多忙の中にもかかわらず参加頂き、熱く議論していただいた皆さんに
感謝いたします。
今日のケースは、オフィス通販事業を手掛けているアスクル株式会社
のケース。
文房具メーカーのプラス株式会社がアスクル事業を分社化し、オフィス
向け通信販売事業の今後の展開に向けて、重要な意思決定を迫られて
いる時代(1990年代後半)のケースでした。
文房具業界ではガリバー的存在のコクヨ(系列販社を傘下に圧倒的な
シェアを有する)に対抗する戦略として、通信販売事業を核に展開して
いこうとするアスクルがどのような手法を取るべきか?
同業他社が手をつけきれていない30人未満のオフィス市場を主なター
ゲットとして設定し、既存の小売店(文房具店)との共存共栄を保つ
流通チャネルの構築や価格設定等、その戦略について議論していきま
した。


ターゲットとしているオフィスの社員が上司から文房具の購入を依頼
されたシーンを想定した場合、どのような消費行動をとるのか。どこの
お店に買いに行くのか、文具だけでなくどのような関連商品まで購入
するのか、などなどを考えながら、通販という形態でのメリット、デメ
リット等も議論していきました。
最終的な論点としては、当時、圧倒的な在庫量や価格攻勢で日本市場に
参入を予定していたカテゴリーキラーと呼ばれるアメリカの「オフィス・
デポ」や「オフィス・マックス」に対抗するにはどのような戦略を取る
べきか、当時の岩田社長の意思決定(3つの案)について議論を進めま
した。
現在、文具関係のカテゴリーキラーが成功を遂げているかを見てみると
結果は明らかですが、当時の判断は非常に難しかったように思えます。
特に玩具業界のカテゴリーキラーである「トイザラス」は現在の日本で
大成功を収めていることを考えると、玩具と文具の違いは何なのか・・・。
塾生間のディスカッションやケースリード役の講師の私見などから導き
出された見解は実に聞き応えのある内容でした。
参加された塾生はいつもより少なかったのですが、非常に内容の濃い
勉強会になりました。

ご多忙の中にもかかわらず参加頂き、熱く議論していただいた皆さんに
感謝いたします。
2013年02月05日
第10回ビジネススクール(P&G「ジョイ」の攻勢)
昨夜は今年最初のビジネススクール(第10回)を開催しました。
今回のケースは、P&G「ジョイ」の攻勢と花王・ライオンの対応
です。
時代は、P&Gが「ジョイ」ブランドで台所用洗剤市場に参入した
1995年から2000年頃。台所用洗剤市場のパイを奪い合う
P&G、花王、ライオンという3強が熾烈な競争状態を迎えていた
時代のケースです。

台所用洗剤の変遷は、1950年代草創期の粉石けんの時代から60
年代には特に主婦の手荒れ防止などへの対応、70年代には環境への
対応や配慮、80年代になると(低)価格競争時代へ・・・、
そして1995年に満を持して、グローバル企業のP&Gが「ジョイ」
でこの市場に参入という時代背景があります。
家事をやっていない私たちも、「ファミリ」「ママレモン」「ママロー
ヤル」「ルナマイルド」「ファミリーフレッシュ」「チャーミーグリ
ーン」などはCMなどでお馴染みだったのですが、メーカーは?と問
われれば・・・。

議論したポイントは、P&Gの成長要因や強みについて。
新成分開発や技術力、顧客ニーズを徹底的に追求したマーケティング力、
斬新なインパクトあるテレビCM(高田順二の突撃レポート)、ブランド
戦略、流通戦略(直販形態への対応、製販同盟)、小売へのソリューシ
ョン型営業の徹底、マーケティング専門部署などをいち早く設置した
組織力などなど、ケースの中から読み取れるキーワードをどんどん意見
として挙げてもらいました。
あらためてP&G社の強さが理解できました。
そうは言いつつも2000年頃になると陰りが見えはじめ、
さてこれからP&Gとして取り組む戦略は・・・。
塾生からは様々な意見がでてきました(現在、市販されているものの含め)。
・健康・環境・安心感を高めた「オーガニック成分」の洗剤開発(機能を
付加)
・ボトルの汚れや両手を上手く活用するためのプッシュ式ボトルの活用
(使用方法の改善、容器に着目)
・手洗いも代用できる洗剤(用途を付加)
・粉末にもどった洗剤の開発(原点に立ち戻る)
・食器洗浄機とタイアップ(家電メーカーとのタイアップ)
・シンク周りまで洗える対応(オールインワン)
・贈答用セットや超高級志向の洗剤(ターゲットの拡大:洗濯用洗剤など
と同様)
・ファッショナブルなデザイン(デザイナーとのコラボ:〔アタックの例〕)
・販売促進、ポイント制の導入(サービス付加)
・アクリルたわしなどの洗剤を使わないスポンジ(洗剤不要論)
などなど。
それぞれのメリット、デメリット、実現可能性などを楽しく議論しながら
進めていきました。
市販価格わずか150円程度の台所用洗剤について、商品開発やブラン
ディング戦略など、多様な観点から真剣に議論した2時間でした。

今回のケースは、P&G「ジョイ」の攻勢と花王・ライオンの対応
です。
時代は、P&Gが「ジョイ」ブランドで台所用洗剤市場に参入した
1995年から2000年頃。台所用洗剤市場のパイを奪い合う
P&G、花王、ライオンという3強が熾烈な競争状態を迎えていた
時代のケースです。

台所用洗剤の変遷は、1950年代草創期の粉石けんの時代から60
年代には特に主婦の手荒れ防止などへの対応、70年代には環境への
対応や配慮、80年代になると(低)価格競争時代へ・・・、
そして1995年に満を持して、グローバル企業のP&Gが「ジョイ」
でこの市場に参入という時代背景があります。
家事をやっていない私たちも、「ファミリ」「ママレモン」「ママロー
ヤル」「ルナマイルド」「ファミリーフレッシュ」「チャーミーグリ
ーン」などはCMなどでお馴染みだったのですが、メーカーは?と問
われれば・・・。

議論したポイントは、P&Gの成長要因や強みについて。
新成分開発や技術力、顧客ニーズを徹底的に追求したマーケティング力、
斬新なインパクトあるテレビCM(高田順二の突撃レポート)、ブランド
戦略、流通戦略(直販形態への対応、製販同盟)、小売へのソリューシ
ョン型営業の徹底、マーケティング専門部署などをいち早く設置した
組織力などなど、ケースの中から読み取れるキーワードをどんどん意見
として挙げてもらいました。
あらためてP&G社の強さが理解できました。
そうは言いつつも2000年頃になると陰りが見えはじめ、
さてこれからP&Gとして取り組む戦略は・・・。
塾生からは様々な意見がでてきました(現在、市販されているものの含め)。
・健康・環境・安心感を高めた「オーガニック成分」の洗剤開発(機能を
付加)
・ボトルの汚れや両手を上手く活用するためのプッシュ式ボトルの活用
(使用方法の改善、容器に着目)
・手洗いも代用できる洗剤(用途を付加)
・粉末にもどった洗剤の開発(原点に立ち戻る)
・食器洗浄機とタイアップ(家電メーカーとのタイアップ)
・シンク周りまで洗える対応(オールインワン)
・贈答用セットや超高級志向の洗剤(ターゲットの拡大:洗濯用洗剤など
と同様)
・ファッショナブルなデザイン(デザイナーとのコラボ:〔アタックの例〕)
・販売促進、ポイント制の導入(サービス付加)
・アクリルたわしなどの洗剤を使わないスポンジ(洗剤不要論)
などなど。
それぞれのメリット、デメリット、実現可能性などを楽しく議論しながら
進めていきました。
市販価格わずか150円程度の台所用洗剤について、商品開発やブラン
ディング戦略など、多様な観点から真剣に議論した2時間でした。

2012年12月19日
第9回ビジネススクール(ミスミのケース)
昨夜は、今年最後のビジネススクールを開催しました。
今回のケースは株式会社ミスミのケースです。
同社は一般的にはあまり耳にすることがない会社ですが、業界内では
革新的な企業として名の通っている会社ではないでしょうか。
現在のミスミも収益力の高い会社ようですが、今回使用したケースは
1993年から1994年にかけて業界では稀なトータルシステムの
構築や医療分野への進出を試みるなど、1963年の創業から20年
ほど経過して新たな意思決定を検討している時のケースでした。

まず最初にミスミの業種って何だろう?ということから考えていきま
した。
メーカーのような商社、卸売業?・・・、自社の事業定義を「購買代
理業」と銘打って、当時は機械金属メーカーの商社的な存在を担って
いたようです。
しかし金型製作や受注加工品製作に卸的な機能が必要なのか?、標準化
が難しい業界の中でミスミの存在価値が果たしてあるのか?などを議論
していきました。
また、ミスミが提唱している「マーケット・アウト」とはどのような考
え方なのか、「マーケット・イン」「プロダクト・アウト」との違いは
どこにあるのか?・・・、当時の考え方としては斬新な手法で存在価値
を高めてきたミスミの成功の鍵(KFS)を挙げながら、更に深い議論
を積み重ねていきました。
ちなみにミスミのKFSとして挙げられたのは以下の3点です。
・協力メーカーの存在
・ミスミの製品開発力
・ローコスト・オペレーション

そして最後に、ミスミの未来戦略として、ケースの最後に提起されていた
・アナログのカタログからパソコン通信網を活用したトータルシステム
(CAD/CAM)の可能性(1994当時はインターネットの普及率は
極めて低い時代です)
・医療分野への進出の可否
などを考えていきました。
普段は取り上げる機会が少ないミスミのような業種においても、塾生の
皆さんたちは、ビジネスモデルの整合性やユーザーニーズの翻訳機能と
いう観点から、自分の業界や業種に照らし合わせながら、あるいは同業
他社の先進事例などと比較しながら議論していく様は、非常に聞き応え
があり、その議論の深さに感心しました。
今回もまた実に楽しく有意義な2時間半でした。
その後、近くの焼鳥屋「かちがらす」でおいしい骨付きカルビを食し
ながら忘年会&第2ラウンドの語り合いをしました。
今年1年間お付合い頂きました講師の皆さま、塾生の皆さまに感謝いた
します。
そして14期は来年3月まで続きますのでまだまだよろしくお願いします。
今回のケースは株式会社ミスミのケースです。
同社は一般的にはあまり耳にすることがない会社ですが、業界内では
革新的な企業として名の通っている会社ではないでしょうか。
現在のミスミも収益力の高い会社ようですが、今回使用したケースは
1993年から1994年にかけて業界では稀なトータルシステムの
構築や医療分野への進出を試みるなど、1963年の創業から20年
ほど経過して新たな意思決定を検討している時のケースでした。

まず最初にミスミの業種って何だろう?ということから考えていきま
した。
メーカーのような商社、卸売業?・・・、自社の事業定義を「購買代
理業」と銘打って、当時は機械金属メーカーの商社的な存在を担って
いたようです。
しかし金型製作や受注加工品製作に卸的な機能が必要なのか?、標準化
が難しい業界の中でミスミの存在価値が果たしてあるのか?などを議論
していきました。
また、ミスミが提唱している「マーケット・アウト」とはどのような考
え方なのか、「マーケット・イン」「プロダクト・アウト」との違いは
どこにあるのか?・・・、当時の考え方としては斬新な手法で存在価値
を高めてきたミスミの成功の鍵(KFS)を挙げながら、更に深い議論
を積み重ねていきました。
ちなみにミスミのKFSとして挙げられたのは以下の3点です。
・協力メーカーの存在
・ミスミの製品開発力
・ローコスト・オペレーション

そして最後に、ミスミの未来戦略として、ケースの最後に提起されていた
・アナログのカタログからパソコン通信網を活用したトータルシステム
(CAD/CAM)の可能性(1994当時はインターネットの普及率は
極めて低い時代です)
・医療分野への進出の可否
などを考えていきました。
普段は取り上げる機会が少ないミスミのような業種においても、塾生の
皆さんたちは、ビジネスモデルの整合性やユーザーニーズの翻訳機能と
いう観点から、自分の業界や業種に照らし合わせながら、あるいは同業
他社の先進事例などと比較しながら議論していく様は、非常に聞き応え
があり、その議論の深さに感心しました。
今回もまた実に楽しく有意義な2時間半でした。
その後、近くの焼鳥屋「かちがらす」でおいしい骨付きカルビを食し
ながら忘年会&第2ラウンドの語り合いをしました。
今年1年間お付合い頂きました講師の皆さま、塾生の皆さまに感謝いた
します。
そして14期は来年3月まで続きますのでまだまだよろしくお願いします。
2012年11月26日
第8回ビジネススクール
本日は先程まで8回目のビジネススクールを開講しており、塾生の
皆さんと熱い議論を交わしていました。

今回のケースは「刈谷豊田総合病院におけるリスクマネジメント」。
病院に関するケースはこれまでも取り扱ってきましたが、医療行為と
収益性の関係や医療サービスに対する評価基準の難しさ、患者さん
なのかお客さんなのか・・・等々、
様々な議論をしながら病院のマネジメントについて考えてきました。
今回の病院はトヨタグループが設立主体の一員となっており、民間の
発想を多く取り入れて第三者から大変高い評価を受けている病院です。
なぜ外部評価が高いのか、その要因は・・・、
医療現場で最も重要である「医療事故を起こさない」ためのリスク
マネジメントがうまく機能しているところにあるというのがケース
教材のなかに事細かに記載されています。
では、他の病院でリスクマネジメントはなされていないのか?
というとそうではないはずです。
今夜はこの病院の特色であるリスクマネジメントの是非に絞って議論
を重ねました。

同院は「事故を起こしたくても起こせない仕組み」を構築することに
より、現場の医師や看護師といったヒトではなく、仕組み(システム)
によって事故原因を解消しようと考えでリスクマネジメントを実行して
います。
しかし、ただでさえ難しいと言われている医療現場でのリスクマネジメ
ントの仕組みをいかに組織になじませるのか、
いかに現場の負担なくリスクマネジメントをまわすシステムの導入が
できるのか、
トップとミドルと現場(理事長、医師、看護師、事務方など)がいかに
公平かつ公正な職場づくりができるのか、
リスクマネジメントを実施することでいかに成功体験(医療事故が減少
する)につながるのか、
リスマネジメントに必要な事務量とその効果(評価)の関係は、
組織あるいは個人にとってマイナスにつながるリスク情報が円滑に上が
ってくるためにはどのようなシステムが必要なのか、
そもそも医療現場に有効なリスクマネジメントとは何か、
などなど、
ケース教材に書かれていない病院現場の状況を考えながら議論を積み重ね
ていきました。

たまたま、今期の塾生には病院事務の経験者や病院で企画を担当されている
方、医療・介護施設の研修講師を務めている方などがいらっしゃるので、
より具体的な方法等についても考えてみました。
もちろん民間企業経営者としての観点や従業員側からの観点等も織り交ぜ
ながらディスカッションしました。
ケース授業では結論めいたまとめ的なものはありませんが、医療現場で
成功しているリスクマネジメントの手法を自分たちの企業の中で活用でき
るのか・・・、
多くのヒントが隠されているケースであったように思えます。
皆さんと熱い議論を交わしていました。

今回のケースは「刈谷豊田総合病院におけるリスクマネジメント」。
病院に関するケースはこれまでも取り扱ってきましたが、医療行為と
収益性の関係や医療サービスに対する評価基準の難しさ、患者さん
なのかお客さんなのか・・・等々、
様々な議論をしながら病院のマネジメントについて考えてきました。
今回の病院はトヨタグループが設立主体の一員となっており、民間の
発想を多く取り入れて第三者から大変高い評価を受けている病院です。
なぜ外部評価が高いのか、その要因は・・・、
医療現場で最も重要である「医療事故を起こさない」ためのリスク
マネジメントがうまく機能しているところにあるというのがケース
教材のなかに事細かに記載されています。
では、他の病院でリスクマネジメントはなされていないのか?
というとそうではないはずです。
今夜はこの病院の特色であるリスクマネジメントの是非に絞って議論
を重ねました。

同院は「事故を起こしたくても起こせない仕組み」を構築することに
より、現場の医師や看護師といったヒトではなく、仕組み(システム)
によって事故原因を解消しようと考えでリスクマネジメントを実行して
います。
しかし、ただでさえ難しいと言われている医療現場でのリスクマネジメ
ントの仕組みをいかに組織になじませるのか、
いかに現場の負担なくリスクマネジメントをまわすシステムの導入が
できるのか、
トップとミドルと現場(理事長、医師、看護師、事務方など)がいかに
公平かつ公正な職場づくりができるのか、
リスクマネジメントを実施することでいかに成功体験(医療事故が減少
する)につながるのか、
リスマネジメントに必要な事務量とその効果(評価)の関係は、
組織あるいは個人にとってマイナスにつながるリスク情報が円滑に上が
ってくるためにはどのようなシステムが必要なのか、
そもそも医療現場に有効なリスクマネジメントとは何か、
などなど、
ケース教材に書かれていない病院現場の状況を考えながら議論を積み重ね
ていきました。

たまたま、今期の塾生には病院事務の経験者や病院で企画を担当されている
方、医療・介護施設の研修講師を務めている方などがいらっしゃるので、
より具体的な方法等についても考えてみました。
もちろん民間企業経営者としての観点や従業員側からの観点等も織り交ぜ
ながらディスカッションしました。
ケース授業では結論めいたまとめ的なものはありませんが、医療現場で
成功しているリスクマネジメントの手法を自分たちの企業の中で活用でき
るのか・・・、
多くのヒントが隠されているケースであったように思えます。
2012年11月07日
第7回ビジネススクール(世田谷美術館)
今日は、先程まで第7回ビジネススクール鳳雛塾を開催していました。
本日のケースは、世田谷美術館。普段良く使用する民間企業のケース
とは趣が異なり、公共美術館のマネジメントについて参加塾生間で熱い
議論を交わしました。

今回のケースリード役(講師)は、梁井先生。さすがに流通業界のプロ
だけあって(バイヤー的感覚)、美術品や芸術品等への造詣も深く、公的
な美術館のケースをマネジメントの観点やマーケティングの観点から実に
巧みにケースリードして頂きました。

世田谷美術館は世田谷区民の美術館として「芸術と素朴」と名付けた展覧
会を通して特色ある取り組みをなされており、国内の美術館の中では特有
な存在と言える美術館のようです。
もちろん海外の美術館と国内のそれを比較した場合、根本的な相違点が多く、
まずは国内における美術館の在り方から議論を始めました。
その後、世田谷美術館の理念や基本方針、人材の登用方法、特別独立行政
法人という組織の在り方、収益モデルの考え方など、特に独自性の強い
部分を議論しながら今後の方向性を考えていきました。

ケースの中でも述べられていた公立美術館の収益性の考え方については、
賛成派、反対派に分かれて、収支構造を分析しながら区民のための美術館
とは何ぞや、という根本的な美術館の存在意義までをつめて考えてみました。
もちろん、公立といえどもターゲットを見据えた企画展の在り方やマーケ
ティング、来館者の満足度向上など、一般企業と変わらない視点から今後
の経営につて議論を進めていきました。
今日の授業でも受講生の皆さんは奥が深く、ポイントを押さえた議論を
交わして頂き、聞き応えのあるとても有意義な時間になりました。
ご参加頂きました皆さん、お疲れ様でした。
本日のケースは、世田谷美術館。普段良く使用する民間企業のケース
とは趣が異なり、公共美術館のマネジメントについて参加塾生間で熱い
議論を交わしました。

今回のケースリード役(講師)は、梁井先生。さすがに流通業界のプロ
だけあって(バイヤー的感覚)、美術品や芸術品等への造詣も深く、公的
な美術館のケースをマネジメントの観点やマーケティングの観点から実に
巧みにケースリードして頂きました。

世田谷美術館は世田谷区民の美術館として「芸術と素朴」と名付けた展覧
会を通して特色ある取り組みをなされており、国内の美術館の中では特有
な存在と言える美術館のようです。
もちろん海外の美術館と国内のそれを比較した場合、根本的な相違点が多く、
まずは国内における美術館の在り方から議論を始めました。
その後、世田谷美術館の理念や基本方針、人材の登用方法、特別独立行政
法人という組織の在り方、収益モデルの考え方など、特に独自性の強い
部分を議論しながら今後の方向性を考えていきました。

ケースの中でも述べられていた公立美術館の収益性の考え方については、
賛成派、反対派に分かれて、収支構造を分析しながら区民のための美術館
とは何ぞや、という根本的な美術館の存在意義までをつめて考えてみました。
もちろん、公立といえどもターゲットを見据えた企画展の在り方やマーケ
ティング、来館者の満足度向上など、一般企業と変わらない視点から今後
の経営につて議論を進めていきました。
今日の授業でも受講生の皆さんは奥が深く、ポイントを押さえた議論を
交わして頂き、聞き応えのあるとても有意義な時間になりました。
ご参加頂きました皆さん、お疲れ様でした。
2012年10月23日
第6回ビジネススクール
昨夜は第6回ビジネススクール鳳雛塾を開催しました。
今回討議したケースは「㈱レインズ・インターナショナル-起業家
輩出機関-」。
㈱レインズ・インターナショナルと聞いても“?”と思う方も多い
ことでしょう。
しかし、牛角、とりでん、かまどか、土間土間、しゃぶしゃぶ温野
菜など多くの外食チェーンを展開している企業と聞くと、「そのお店
には行ったことがあるよ」という方も多いのではないでしょうか。

このケースは2005年9月に書かれたケースなので、今から約7年
程前にさかのぼり、フランチャイズとして展開する外食チェーンが
隆盛を極めていた時代の話です。この時期のレインズ社は、コンビ
ニエンスストアのampm(エーエム・ピーエムジャパン)や高級
スーパーの成城石井までも買収して傘下にするなど、業績が伸びて
いた頃です。
不動産業者として設立したレインズ社が業態転換したのは、マクド
ナルドのオペレーションシステムへの関心の高まりと1999年から
フランチャイズビジネスの育成・支援事業を全国展開してきた
㈱ベンチャーリンク社(本年3月に会社更生法手続き)との出会い
からです。
フランチャイズシステムが普及していない時代は、異業種へ参入す
るためには、ノウハウや流通システムの構築、人材確保、販路開拓
など、多大なる労力が必要だったのですが、フランチャイズシステム
の導入によって、比較的簡単に(実際は簡単ではないでしょうが)
異業種参入ができるようになっています。

果たして、
レインズ・インターナショナルが目指すビジネスの将来像は?
ベンチャーリンク社との提携に問題はないのか?
主力業務(特に牛角)への選択と集中に進むべきか?
新たなFCビジネスを展開し多角化していくべきか?
第3の路へ進むべきか?・・・などなど
様々な観点からレインズ社の進むべき戦略や将来構想を議論していき
ました。
またまた昨夜もあっという間の2時間が過ぎていきました。
今回討議したケースは「㈱レインズ・インターナショナル-起業家
輩出機関-」。
㈱レインズ・インターナショナルと聞いても“?”と思う方も多い
ことでしょう。
しかし、牛角、とりでん、かまどか、土間土間、しゃぶしゃぶ温野
菜など多くの外食チェーンを展開している企業と聞くと、「そのお店
には行ったことがあるよ」という方も多いのではないでしょうか。

このケースは2005年9月に書かれたケースなので、今から約7年
程前にさかのぼり、フランチャイズとして展開する外食チェーンが
隆盛を極めていた時代の話です。この時期のレインズ社は、コンビ
ニエンスストアのampm(エーエム・ピーエムジャパン)や高級
スーパーの成城石井までも買収して傘下にするなど、業績が伸びて
いた頃です。
不動産業者として設立したレインズ社が業態転換したのは、マクド
ナルドのオペレーションシステムへの関心の高まりと1999年から
フランチャイズビジネスの育成・支援事業を全国展開してきた
㈱ベンチャーリンク社(本年3月に会社更生法手続き)との出会い
からです。
フランチャイズシステムが普及していない時代は、異業種へ参入す
るためには、ノウハウや流通システムの構築、人材確保、販路開拓
など、多大なる労力が必要だったのですが、フランチャイズシステム
の導入によって、比較的簡単に(実際は簡単ではないでしょうが)
異業種参入ができるようになっています。

果たして、
レインズ・インターナショナルが目指すビジネスの将来像は?
ベンチャーリンク社との提携に問題はないのか?
主力業務(特に牛角)への選択と集中に進むべきか?
新たなFCビジネスを展開し多角化していくべきか?
第3の路へ進むべきか?・・・などなど
様々な観点からレインズ社の進むべき戦略や将来構想を議論していき
ました。
またまた昨夜もあっという間の2時間が過ぎていきました。
2012年10月06日
第5回ビジネススクール
昨夜は、第5回目のビジネススクールを開催しました。
今回のケースは、2005年に香川県を活性化する目的で立ち上げ
られた地域密着型情報検索サイトの運営をしていた有限会社ドコイコ
(後に株式会社に)のケース。

当時の香川もほかの地方都市と変わらず、郊外大型ショッピングセンター
の進出に伴い、中心商店街が見る影もなく衰退化し、地域が疲弊していた
頃だった。そんな地元の状況を憂いた若者(河野社長)がウェブサービス
を提供して地域を活性化したい、地元の元気を取り戻したい、そんな熱い
想いで立ちあげたベンチャー企業であった。
当時のインターネット普及率はまだ低く、これから飛躍的に伸びていく
だろうという時代背景にも乗って、ドコイコのビジネスモデルは時代に
マッチし、事業は順調に進展していった。各方面からも大きな期待を受
け、社長は地域活性化の成功者としてもてはやされ華々しい将来を迎え
るはずだった。

しかし、段々歯車が噛み合わなくなり組織内の分裂や多角化した事業の
撤退、競合他社との競争激化など経営環境は著しく苦しくなっていった。
このような状況下で、どのような手を打つのか、これからどのような
戦略を打ち立てていくのか、参加した塾生間で様々な議論を繰り広げ
ていきました。
当然、現状から考えると、地域SNSの隆盛やポータルサイト運営の
在り方、またはフリーペーパー発行等の成否については、ある程度の
流れを読むことはできますが、その当時はどうだったのか?
少し時計の針を戻して考えてもらいました。
果たして、当時のビジネスモデルとして妥当だったのか?、若い社長
の経営手腕はどうだったのか?、パートナーとの関係は?、この会社
の特色でもあるバンド型組織は“あり”なのか?・・・などなど。

地域を活性化するとはどういうことなのか、ということと合わせて
ドコイコのマネジメントを議論しました。
昨夜もあっという間に2時間半が過ぎていました。
第14期受講生の皆さん、毎回熱い議論を有り難うございます。
今回のケースは、2005年に香川県を活性化する目的で立ち上げ
られた地域密着型情報検索サイトの運営をしていた有限会社ドコイコ
(後に株式会社に)のケース。

当時の香川もほかの地方都市と変わらず、郊外大型ショッピングセンター
の進出に伴い、中心商店街が見る影もなく衰退化し、地域が疲弊していた
頃だった。そんな地元の状況を憂いた若者(河野社長)がウェブサービス
を提供して地域を活性化したい、地元の元気を取り戻したい、そんな熱い
想いで立ちあげたベンチャー企業であった。
当時のインターネット普及率はまだ低く、これから飛躍的に伸びていく
だろうという時代背景にも乗って、ドコイコのビジネスモデルは時代に
マッチし、事業は順調に進展していった。各方面からも大きな期待を受
け、社長は地域活性化の成功者としてもてはやされ華々しい将来を迎え
るはずだった。

しかし、段々歯車が噛み合わなくなり組織内の分裂や多角化した事業の
撤退、競合他社との競争激化など経営環境は著しく苦しくなっていった。
このような状況下で、どのような手を打つのか、これからどのような
戦略を打ち立てていくのか、参加した塾生間で様々な議論を繰り広げ
ていきました。
当然、現状から考えると、地域SNSの隆盛やポータルサイト運営の
在り方、またはフリーペーパー発行等の成否については、ある程度の
流れを読むことはできますが、その当時はどうだったのか?
少し時計の針を戻して考えてもらいました。
果たして、当時のビジネスモデルとして妥当だったのか?、若い社長
の経営手腕はどうだったのか?、パートナーとの関係は?、この会社
の特色でもあるバンド型組織は“あり”なのか?・・・などなど。

地域を活性化するとはどういうことなのか、ということと合わせて
ドコイコのマネジメントを議論しました。
昨夜もあっという間に2時間半が過ぎていました。
第14期受講生の皆さん、毎回熱い議論を有り難うございます。
2012年09月25日
第4回ビジネススクール(カタリバのケース)
本日は先程まで第4回目のビジネススクールを開催していました。
今回勉強したケースは、NPO法人カタリバのケース。ケースリード
は秋満講師に担当していただきました。
カタリバのケースは、私たち鳳雛塾が取り組んでいるキャリア教育を
主体とした教育モデルで事業内容が非常に似通っており、塾生の議論
を通して私たち自身が一番勉強になるケースでした。


カタリバの事業モデルは、先生や親のような「タテ」のつながりでも
なく、同世代の友達関係のような「ヨコ」のつながりでもなく、高校生
から見て少し先輩にあたる大学生の位置づけ、すなわち「ナナメ」の
つながりの中でコミュニケーションを図る学び合いのモデル。
高校生と大学生の「語り場」が新たな化学反応を巻き起こすキャリア
教育の場となっており、そのつながりが大きく拡がって子ども達に
良い影響を与えている事業です。
今回の授業には、たまたまキャリア教育事業やケースメソッド授業に
関心のある有明高専の3年生が2名、自ら個展を開催した佐賀北高芸術
専攻の高校3年生が1名参加してくれましたので、高校生としての意見
も述べてもらいました。
また14期生には高校の先生や大学で働いている職員の方もいらっしゃ
るので、高校教師としての立場、大学職員としての立場で「カタリバ」
の有効性についいて考えを述べてもらいました。


ほとんどの塾生は、一般企業の経営者であったり、職員であったりし
ますので、NPO法人との関係が薄く、公共機関との関係性や社会貢献
活動の是非、ボランティアとの関わり方などわかりづらい事例もあった
ようですが、社会の問題解決等に取り組むNPOの位置づけ等を再認識
して頂いたのではないでしょうか。
大きな論点として、NPOとしての使命は、NPOの生み出す価値とは、
NPOの有する経営資源とは、NPOとして社会にどう役立っているのか、
その活動が社会のニーズを満たしているのか・・・。
等々を議論してもらいました。

参加した塾生の活発な討議により、今日もあっという間に2時間が経過
しました。
参加いただいた塾生の皆さま、遅くまでお疲れ様でした。
今回勉強したケースは、NPO法人カタリバのケース。ケースリード
は秋満講師に担当していただきました。
カタリバのケースは、私たち鳳雛塾が取り組んでいるキャリア教育を
主体とした教育モデルで事業内容が非常に似通っており、塾生の議論
を通して私たち自身が一番勉強になるケースでした。


カタリバの事業モデルは、先生や親のような「タテ」のつながりでも
なく、同世代の友達関係のような「ヨコ」のつながりでもなく、高校生
から見て少し先輩にあたる大学生の位置づけ、すなわち「ナナメ」の
つながりの中でコミュニケーションを図る学び合いのモデル。
高校生と大学生の「語り場」が新たな化学反応を巻き起こすキャリア
教育の場となっており、そのつながりが大きく拡がって子ども達に
良い影響を与えている事業です。
今回の授業には、たまたまキャリア教育事業やケースメソッド授業に
関心のある有明高専の3年生が2名、自ら個展を開催した佐賀北高芸術
専攻の高校3年生が1名参加してくれましたので、高校生としての意見
も述べてもらいました。
また14期生には高校の先生や大学で働いている職員の方もいらっしゃ
るので、高校教師としての立場、大学職員としての立場で「カタリバ」
の有効性についいて考えを述べてもらいました。


ほとんどの塾生は、一般企業の経営者であったり、職員であったりし
ますので、NPO法人との関係が薄く、公共機関との関係性や社会貢献
活動の是非、ボランティアとの関わり方などわかりづらい事例もあった
ようですが、社会の問題解決等に取り組むNPOの位置づけ等を再認識
して頂いたのではないでしょうか。
大きな論点として、NPOとしての使命は、NPOの生み出す価値とは、
NPOの有する経営資源とは、NPOとして社会にどう役立っているのか、
その活動が社会のニーズを満たしているのか・・・。
等々を議論してもらいました。

参加した塾生の活発な討議により、今日もあっという間に2時間が経過
しました。
参加いただいた塾生の皆さま、遅くまでお疲れ様でした。
2012年09月07日
MKタクシーの戦略
本日は先程まで第3回ビジネススクールを開催していました。

今回のケースは「株式会社エムケイ」。
京都のMKタクシーと言えば皆さんもお分かりになるのでは・・・。
時はMKタクシーが東京進出を果たした1998年。京都での
成功事例が東京という商圏で成功しうるのかどうか・・・。
(今ではお隣の福岡県にも進出していますが)
企業設立時からの経緯を研究しながら、今後の戦略について塾生
間で活発な議論を行ないました。
講師は、ビジネススクール鳳雛塾第1期から講師を担当してもらっ
ている梁井先生。鋭い洞察力と分析力、素晴らしい経歴をお持ちの
方で、塾生の意見に様々な角度からメスを入れていかれます。

まずはMKタクシーに乗車したことのある方からの意見を参考に
競合他社との違いから分析していきました。
運転手の人事管理制度から教育制度、タクシー運賃の低価格戦略、
徹底したお客様サービス、業界特有の規制との戦い、「ハナエ・
モリ」デザインの制服等々
МKタクシーの差別化戦略を挙げていけばきりがありません。
その中で青木社長が目指したものは何か。MKの競争優位性は
どこにあるのか・・・。
多様な意見が塾生から出てきました。

最終的には経営戦略論をもとにMKの強さと今後の戦略について
考えていきました。
あらためてMKの面白さを実感したあっという間の2時間でした。

今回のケースは「株式会社エムケイ」。
京都のMKタクシーと言えば皆さんもお分かりになるのでは・・・。
時はMKタクシーが東京進出を果たした1998年。京都での
成功事例が東京という商圏で成功しうるのかどうか・・・。
(今ではお隣の福岡県にも進出していますが)
企業設立時からの経緯を研究しながら、今後の戦略について塾生
間で活発な議論を行ないました。
講師は、ビジネススクール鳳雛塾第1期から講師を担当してもらっ
ている梁井先生。鋭い洞察力と分析力、素晴らしい経歴をお持ちの
方で、塾生の意見に様々な角度からメスを入れていかれます。

まずはMKタクシーに乗車したことのある方からの意見を参考に
競合他社との違いから分析していきました。
運転手の人事管理制度から教育制度、タクシー運賃の低価格戦略、
徹底したお客様サービス、業界特有の規制との戦い、「ハナエ・
モリ」デザインの制服等々
МKタクシーの差別化戦略を挙げていけばきりがありません。
その中で青木社長が目指したものは何か。MKの競争優位性は
どこにあるのか・・・。
多様な意見が塾生から出てきました。

最終的には経営戦略論をもとにMKの強さと今後の戦略について
考えていきました。
あらためてMKの面白さを実感したあっという間の2時間でした。
2012年08月31日
第2回ビジネススクール
今日は、先程まで第2回ビジネススクールを開催し、塾生の
皆さんと熱い議論を交わしていました。

今日の題材(ケース教材)は、「大丸の営業改革」。
講師は、以前百貨店に勤務した経験のある秋満講師に担当して
いただきました。

時は1997年。国内の個人消費が低迷を続ける中で、高級ブラ
ンド専門店が路面展開を進め、百貨店離れに拍車がかかっていた
頃の話です。
当時の大丸の社長であった奥田社長が抜本的な体質改善策として
打ち立てた「新百貨店マネジメント」という戦略について、ディス
カッションを行ないました。

当時の百貨店業界では珍しかった、様々な改革(4つの改革)を強
力に推進したことで業績は向上したものの、企業成長につながって
いるのか、コストダウンだけを強いる止血戦略ではないのか・・・。
本日の議論は、成長戦略を軸にさまざまな立場からの意見が飛び交
いました。
今回は全員でディスカッションをする前に4~5人でグループディス
カッションを行ない、事前学習(宿題)してきた内容をグループで
確認し合いました。また、今回のケースには簡単な財務諸表の見方
や考え方などを検討する事項も含まれており、経営分析手法なども
学びました。

もちろん、ケースメソッドの授業では「正解」と言うものはありま
せんが、それぞれの塾生が奥田社長の立場や自分の立場に置き換え
て考えてくれたのではないでしょうか。
あっという間に2時間半が過ぎてしまった楽しい授業でした。
参加いただきました塾生の皆さまお疲れ様でした。
皆さんと熱い議論を交わしていました。

今日の題材(ケース教材)は、「大丸の営業改革」。
講師は、以前百貨店に勤務した経験のある秋満講師に担当して
いただきました。

時は1997年。国内の個人消費が低迷を続ける中で、高級ブラ
ンド専門店が路面展開を進め、百貨店離れに拍車がかかっていた
頃の話です。
当時の大丸の社長であった奥田社長が抜本的な体質改善策として
打ち立てた「新百貨店マネジメント」という戦略について、ディス
カッションを行ないました。

当時の百貨店業界では珍しかった、様々な改革(4つの改革)を強
力に推進したことで業績は向上したものの、企業成長につながって
いるのか、コストダウンだけを強いる止血戦略ではないのか・・・。
本日の議論は、成長戦略を軸にさまざまな立場からの意見が飛び交
いました。
今回は全員でディスカッションをする前に4~5人でグループディス
カッションを行ない、事前学習(宿題)してきた内容をグループで
確認し合いました。また、今回のケースには簡単な財務諸表の見方
や考え方などを検討する事項も含まれており、経営分析手法なども
学びました。

もちろん、ケースメソッドの授業では「正解」と言うものはありま
せんが、それぞれの塾生が奥田社長の立場や自分の立場に置き換え
て考えてくれたのではないでしょうか。
あっという間に2時間半が過ぎてしまった楽しい授業でした。
参加いただきました塾生の皆さまお疲れ様でした。
2012年08月21日
第14期ビジネススクール開講!!
昨夜から第14期のビジネススクールをスタートしました。
今期の塾生は24名、アドバイザー、講師、スタッフ等も含めて
昨日は30名程度で開講式を行ないました。

1999年に開講した第1期から講師を勤めて頂いている飯盛先生
を講師に、鳳雛塾の紹介とショートケースを使ったケースメソッド
授業、そして塾生の自己紹介を行ないました。

今期の塾生は遠路はるばる北九州や長崎からも参加されており、社会
人を中心とした構成になっています。
昨日の議論でも社会人らしい様々な意見が飛び交い、2時間があっと
いう間に過ぎていきました。

これから2月まで12回シリーズで実施しますが、塾生の方々と前向
きな議論を通して楽しんでいくつもりです。
塾生の皆さん、よろしくお願いします。
今期の塾生は24名、アドバイザー、講師、スタッフ等も含めて
昨日は30名程度で開講式を行ないました。

1999年に開講した第1期から講師を勤めて頂いている飯盛先生
を講師に、鳳雛塾の紹介とショートケースを使ったケースメソッド
授業、そして塾生の自己紹介を行ないました。

今期の塾生は遠路はるばる北九州や長崎からも参加されており、社会
人を中心とした構成になっています。
昨日の議論でも社会人らしい様々な意見が飛び交い、2時間があっと
いう間に過ぎていきました。

これから2月まで12回シリーズで実施しますが、塾生の方々と前向
きな議論を通して楽しんでいくつもりです。
塾生の皆さん、よろしくお願いします。
2012年08月07日
第14期ビジネススクール募集開始!!
2012年06月12日
ビジネススクール開催
今夜は、久し振りにビジネススクールの授業を実施しました。
平成24年度の初のケース授業ということで、ケースメソッド
授業の体験版としてオープンセミナー形式で開催しました。
参加者は多くの大学生を含む約50名。社会人と大学生がケース
ディスカッションを通して、その面白さや奥の深さを体験しま
した。

冒頭にビジネススクール設立の立役者である慶應義塾大学環境
情報学部の飯盛先生に、慶應の研究室から遠隔システムを使って
挨拶をして頂き、授業がスタートしました。
今回のケースは、ある百貨店のテナントとして入居している
コーヒーショップが引き起こした漏水事故のケース。
豪華な大理石の床をコーヒーで汚したテナントショップに原状
復旧を要求する百貨店側の意見に賛同するのか、テナント側の
意見に賛同するのか、それぞれの見解を述べながら、議論は深ま
っていきました。
最終的に諸悪の根源はどこにあるのか、この難局をどう乗り切る
のか、両者にとって成果をあげるためには何が必要なのか・・・。

今回の講師は、鳳雛塾設立当初からケースリードを担当して頂い
ている梁井講師。卓越したケースリードと豊かな社会経験をもと
にケースをリードしていただきました。

今後、第14期ビジネススクールを開催する準備に取り掛かります。
ケースメソッド授業に興味関心のある方は是非、御声かけ下さい。
講座受講の考え方や世の中を見る視点、働き方が変わるかもしれ
ませんよ。
平成24年度の初のケース授業ということで、ケースメソッド
授業の体験版としてオープンセミナー形式で開催しました。
参加者は多くの大学生を含む約50名。社会人と大学生がケース
ディスカッションを通して、その面白さや奥の深さを体験しま
した。

冒頭にビジネススクール設立の立役者である慶應義塾大学環境
情報学部の飯盛先生に、慶應の研究室から遠隔システムを使って
挨拶をして頂き、授業がスタートしました。
今回のケースは、ある百貨店のテナントとして入居している
コーヒーショップが引き起こした漏水事故のケース。
豪華な大理石の床をコーヒーで汚したテナントショップに原状
復旧を要求する百貨店側の意見に賛同するのか、テナント側の
意見に賛同するのか、それぞれの見解を述べながら、議論は深ま
っていきました。
最終的に諸悪の根源はどこにあるのか、この難局をどう乗り切る
のか、両者にとって成果をあげるためには何が必要なのか・・・。

今回の講師は、鳳雛塾設立当初からケースリードを担当して頂い
ている梁井講師。卓越したケースリードと豊かな社会経験をもと
にケースをリードしていただきました。

今後、第14期ビジネススクールを開催する準備に取り掛かります。
ケースメソッド授業に興味関心のある方は是非、御声かけ下さい。
講座受講の考え方や世の中を見る視点、働き方が変わるかもしれ
ませんよ。
2012年05月25日
鳳雛塾オープンセミナー開催!!
第14期鳳雛塾のプレイベントとして
「オープンセミナー」(詳細下記)を開催します。
このオープンセミナーは、ビジネススクールの体験版として開催します。
ビジネススクールに関心のある方、ケースメソッド授業に関心のある方など、
奮ってご参加ください。
(オープンセミナーの参加費は無料です)
記
開催日時 2012年6月12日(火)19:00~21:00
終了後、会場内で簡単な交流会を開催します(21:00~22:00)
会場 佐賀市 i スクエアビル5階会議室(大・中会議室)
(佐賀市駅前中央1-8-32)
対象者 ビジネススクールに関心のある社会人や大学生など
定員 定員50名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
参加費 無料(オープンセミナーは無料です)
※第14期鳳雛塾に入塾希望の方はあらためて参加募集をします。
第14期鳳雛塾は参加費が必要です。
プログラム
19:00~ ビジネススクール鳳雛塾の取り組み説明
19:20~ ケースメソッド授業(体験版)
参加者には事前にケース教材をメールにて配布いたします
ケース教材については現在検討中です
20:45~ 第14期鳳雛塾(ビジネススクール)の開催概要説明(ご案内)
21:00~ セミナー終了後、簡単な交流会を開催します。
21:45~ 会場片付け
22:00 解散
お申込み方法 鳳雛塾のWEB(イベント情報)からお申し込みができます
http://www.housuu.jp/main/4.html
お問い合わせ NPO法人鳳雛塾
TEL/FAX 0952-28-8959
パンフレット(詳細)はこちらから
http://www.housuu.jp/site_files/file/jigyo/business/open-semi.pdf

「オープンセミナー」(詳細下記)を開催します。
このオープンセミナーは、ビジネススクールの体験版として開催します。
ビジネススクールに関心のある方、ケースメソッド授業に関心のある方など、
奮ってご参加ください。
(オープンセミナーの参加費は無料です)
記
開催日時 2012年6月12日(火)19:00~21:00
終了後、会場内で簡単な交流会を開催します(21:00~22:00)
会場 佐賀市 i スクエアビル5階会議室(大・中会議室)
(佐賀市駅前中央1-8-32)
対象者 ビジネススクールに関心のある社会人や大学生など
定員 定員50名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
参加費 無料(オープンセミナーは無料です)
※第14期鳳雛塾に入塾希望の方はあらためて参加募集をします。
第14期鳳雛塾は参加費が必要です。
プログラム
19:00~ ビジネススクール鳳雛塾の取り組み説明
19:20~ ケースメソッド授業(体験版)
参加者には事前にケース教材をメールにて配布いたします
ケース教材については現在検討中です
20:45~ 第14期鳳雛塾(ビジネススクール)の開催概要説明(ご案内)
21:00~ セミナー終了後、簡単な交流会を開催します。
21:45~ 会場片付け
22:00 解散
お申込み方法 鳳雛塾のWEB(イベント情報)からお申し込みができます
http://www.housuu.jp/main/4.html
お問い合わせ NPO法人鳳雛塾
TEL/FAX 0952-28-8959
パンフレット(詳細)はこちらから
http://www.housuu.jp/site_files/file/jigyo/business/open-semi.pdf
2012年03月05日
第13期ビジネススクール最終回
ちょっと遅い報告になりましたが、3月2日金曜日の夜は
第13期ビジネススクール鳳雛塾の最終回(13回目)を
開催しました。
過去の期では最終回に塾生による事業プレゼンをしてもらう
こともありましたが、13期は最後までケースメソッド授業
を受講してもらい、塾生の皆さんで最期のディスカッション
を行ないました。


今回のケースは「株式会社キッズベースキャンプ」。東京都
世田谷区など東急沿線沿いを主な拠点とする民間版学童保育
施設です。
佐賀では見かけない学童保育の形態ですが、東京ではケース
作成時点(2009年7月)で14店舗、会員数が1,700人
を超える規模となっています。
キッズコーチと呼ばれる子どもたちの指導者、特色ある顧客の
設定や対象市場、明確な事業コンセプトや提供するサービス、
業界では稀な人事制度など、他者との差別化を明確にした事業
展開で成功している会社です。
今回のディスカッションでは、特にこの会社のユニークさや
事業戦略(マーケティング戦略やM&A等)、従業員のモチベー
ションの持ち方などを軸に熱い議論をしていきました。


全国的に少子化が叫ばれる中にあっても、同社の対象とする市場
では人口、児童・生徒数は増加傾向にあり、共働きをする世帯も
増加しています。公的な学童保育だけでは満たされない保護者が
これから求めるニーズとは・・・。
一転、このビジネスを我らがご当地佐賀で展開することは可能な
のか?塾生の意見は・・・。
私達鳳雛塾が展開しているキャリア教育事業と相通じる部分が
多いと思っていたこのビジネス、確かに子どもたちへ提供する
サービスは似通っていますが、根本的な違いがあるようです。
最終回に「教育のケース」を勉強させてもらい、我々事務局と
しても大変有意義な時間となりました。
活発な議論をして頂きました塾生の皆さん、お疲れ様でした。
そして第13期のビジネススクールに関わって頂きました講師
の皆様、塾生やオブザーバーの皆様、事務局スタッフの皆さん
今期を盛り上げて頂き、有り難うございました。
また14期でお逢いしましょう。
第13期ビジネススクール鳳雛塾の最終回(13回目)を
開催しました。
過去の期では最終回に塾生による事業プレゼンをしてもらう
こともありましたが、13期は最後までケースメソッド授業
を受講してもらい、塾生の皆さんで最期のディスカッション
を行ないました。


今回のケースは「株式会社キッズベースキャンプ」。東京都
世田谷区など東急沿線沿いを主な拠点とする民間版学童保育
施設です。
佐賀では見かけない学童保育の形態ですが、東京ではケース
作成時点(2009年7月)で14店舗、会員数が1,700人
を超える規模となっています。
キッズコーチと呼ばれる子どもたちの指導者、特色ある顧客の
設定や対象市場、明確な事業コンセプトや提供するサービス、
業界では稀な人事制度など、他者との差別化を明確にした事業
展開で成功している会社です。
今回のディスカッションでは、特にこの会社のユニークさや
事業戦略(マーケティング戦略やM&A等)、従業員のモチベー
ションの持ち方などを軸に熱い議論をしていきました。


全国的に少子化が叫ばれる中にあっても、同社の対象とする市場
では人口、児童・生徒数は増加傾向にあり、共働きをする世帯も
増加しています。公的な学童保育だけでは満たされない保護者が
これから求めるニーズとは・・・。
一転、このビジネスを我らがご当地佐賀で展開することは可能な
のか?塾生の意見は・・・。
私達鳳雛塾が展開しているキャリア教育事業と相通じる部分が
多いと思っていたこのビジネス、確かに子どもたちへ提供する
サービスは似通っていますが、根本的な違いがあるようです。
最終回に「教育のケース」を勉強させてもらい、我々事務局と
しても大変有意義な時間となりました。
活発な議論をして頂きました塾生の皆さん、お疲れ様でした。
そして第13期のビジネススクールに関わって頂きました講師
の皆様、塾生やオブザーバーの皆様、事務局スタッフの皆さん
今期を盛り上げて頂き、有り難うございました。
また14期でお逢いしましょう。
2012年02月17日
第12回ビジネススクール
本日は先程まで第12回ビジネススクールを開催していました。
第13期も終講まであと2回。今日は高校生の飛び入り参加など数名
のオブザーバー参加もあり、総勢20名以上で議論を交わしました。


本日のケースは、今期初の試みとなる「非営利組織」のケースで「特定
非営利活動法人まごころ」の教材を使用して非営利組織のマネジメント
について考えてみました。
最近の傾向として社会起業家(SB)への期待が高まる中、NPO法人
の設立が増加しており、すでに国内には30,000以上のNPO法人
が存在するそうです。
そういった自分たち(鳳雛塾)もNPOなわけで、本日のケース内容は、
私自身、当事者意識(身につまされる思い)で聞き入っていました。
このケースは、高齢者向け訪問(介護)サービスの草分け的なNPOと
して立ちあがったようですが、ケース作成時点ではどちらかというと
人事面、予算面、事務管理面においても上手くまわっておらず、社員や
有償ボランティアからの不満も多く、サービスの質も低下している傾向
にあるようです。最終的には立ち上げにかかわった事務局長がその座を
去るなど・・・。
議論は、そもそもボランティアとは、特定非営利活動法人とは、から始
まりましたが、企業経営者や民間経験者、大学生などには馴染みが薄い
こともあって様々な議論が飛び交いました。
ケース企業においても、今取り組むべき優先順位は何かという問いに対
して、
・社員やボランティアのモチベーションアップ
・収益力の確保
・新たな委託事業への取り組み
・事務管理面の整備
など、意見が分かれました。


NPOのマネジメント力向上、ミッション経営、多角的な活動資金調達、
意識の高い社員の確保やモチベーションの維持、給料のアップ、収益力
の向上や事業拡大などなど、様々な策は考えられますが、一体何のために、
誰のために、根幹となるミッションは・・・。
今後、社会に存在する多くの課題解決のために、非営利組織の存在価値
が高まってくることは間違いないと思われますが、果たしてそこに関わる
人たちはハッピーなのか?
まだまだ考えなければいけないことは山ほどありそうです。
第13期も終講まであと2回。今日は高校生の飛び入り参加など数名
のオブザーバー参加もあり、総勢20名以上で議論を交わしました。


本日のケースは、今期初の試みとなる「非営利組織」のケースで「特定
非営利活動法人まごころ」の教材を使用して非営利組織のマネジメント
について考えてみました。
最近の傾向として社会起業家(SB)への期待が高まる中、NPO法人
の設立が増加しており、すでに国内には30,000以上のNPO法人
が存在するそうです。
そういった自分たち(鳳雛塾)もNPOなわけで、本日のケース内容は、
私自身、当事者意識(身につまされる思い)で聞き入っていました。
このケースは、高齢者向け訪問(介護)サービスの草分け的なNPOと
して立ちあがったようですが、ケース作成時点ではどちらかというと
人事面、予算面、事務管理面においても上手くまわっておらず、社員や
有償ボランティアからの不満も多く、サービスの質も低下している傾向
にあるようです。最終的には立ち上げにかかわった事務局長がその座を
去るなど・・・。
議論は、そもそもボランティアとは、特定非営利活動法人とは、から始
まりましたが、企業経営者や民間経験者、大学生などには馴染みが薄い
こともあって様々な議論が飛び交いました。
ケース企業においても、今取り組むべき優先順位は何かという問いに対
して、
・社員やボランティアのモチベーションアップ
・収益力の確保
・新たな委託事業への取り組み
・事務管理面の整備
など、意見が分かれました。


NPOのマネジメント力向上、ミッション経営、多角的な活動資金調達、
意識の高い社員の確保やモチベーションの維持、給料のアップ、収益力
の向上や事業拡大などなど、様々な策は考えられますが、一体何のために、
誰のために、根幹となるミッションは・・・。
今後、社会に存在する多くの課題解決のために、非営利組織の存在価値
が高まってくることは間違いないと思われますが、果たしてそこに関わる
人たちはハッピーなのか?
まだまだ考えなければいけないことは山ほどありそうです。
2012年02月06日
白熱した第11回ビジネススクール
金曜日の夜はビジネススクールを開催しました。
今回のケース教材は「青梅慶友病院」。
これまで青梅慶友病院については知る機会がありませんでしたが
ケースを勉強してびっくり。徹底的にサービス業的な感覚で病院
経営をされている同院の理念や考え方に驚かされました。


塾生の議論の論点も医療行為とサービス精神のポイントに集中し、
医療とは、介護とは、サービス産業とはという観点やお客様(ここ
では患者様)満足度、従業員満足度(モチベーション)の観点など
について議論が盛り上がりました。
今期は塾生の中に、医学部生や介護福祉関係者、企業経営者など
様々な立場の方がいらっしゃいますので、今回のケースは、まさに
当事者感覚での発言があり、白熱した議論となりました。


青梅慶友病院のケースは、企業経営を考える際に多くのポイントを
与えてくれる非常に面白いケースでした。
今回のケース教材は「青梅慶友病院」。
これまで青梅慶友病院については知る機会がありませんでしたが
ケースを勉強してびっくり。徹底的にサービス業的な感覚で病院
経営をされている同院の理念や考え方に驚かされました。


塾生の議論の論点も医療行為とサービス精神のポイントに集中し、
医療とは、介護とは、サービス産業とはという観点やお客様(ここ
では患者様)満足度、従業員満足度(モチベーション)の観点など
について議論が盛り上がりました。
今期は塾生の中に、医学部生や介護福祉関係者、企業経営者など
様々な立場の方がいらっしゃいますので、今回のケースは、まさに
当事者感覚での発言があり、白熱した議論となりました。


青梅慶友病院のケースは、企業経営を考える際に多くのポイントを
与えてくれる非常に面白いケースでした。
2012年01月25日
第10回ビジネススクール
今夜は先程まで大学生・社会人向けのビジネススクールを実施
していました。ケースリーダーの秋満さん、塾生の皆さんの活発
な議論が絶えることなく予定の21時を大幅に超過して先程終了
しました。
今日議論したケースは、地方温泉旅館の事業再生のケース。
まず最終に受講生の経験談から、これまで行った温泉旅館で印象
に残っているところは?という問いに対して、黒川、湯布院、別府、
指宿、という九州の代表的な温泉のほか、箱根や道後などの声も。
もちろん佐賀の温泉、古湯や嬉野、武雄も挙がっていました。
その目的は・・・、というと個別の旅館を目的としているのではなく、
観光を目的に宿泊先を選ぶ、という意見が多かったようです。


さて、今回のケースの内容は、1992年に経営者であるご主人が
亡くなったことで事業を引き継いだ奥さんが老舗旅館を切り盛りし
ていくケース。それまでは順風満帆であった旅館を続けていくべきか、
M&Aで売却すべきか、という議論からはじまり、経営革新計画の
認定を受けて大幅な施設改修を行なって新しいタイプのホテル型旅館
として再生していくなど、様々な観点から議論しました。
ホテル・旅館業界においては、需要動向の目まぐるしい変化の中で
繁閑期のバラツキやリピーター客確保の難しさ、その上装置産業型
経営やサービス人員の確保など固定費がかさばる中で、なかなか
経営革新が難しい・・・、しかも借入金も多い・・・。
これからの地方温泉旅館はどうあるべきか、熟考していきました。


今回は財務諸表の分析(損益分岐点や限界利益)や需要動向に合わ
せたマーケティングの手法、どの時点で経営を諦めるかなども、
議論の対象となりました。
佐賀でも同じような事例として、富士町の古湯や嬉野などは同じ
ような問題を抱えているかもしれません。特に地方の旅館業界に
おいては、地域協業が必要か否かなど。
本日も議論が尽きることはありませんでした。
していました。ケースリーダーの秋満さん、塾生の皆さんの活発
な議論が絶えることなく予定の21時を大幅に超過して先程終了
しました。
今日議論したケースは、地方温泉旅館の事業再生のケース。
まず最終に受講生の経験談から、これまで行った温泉旅館で印象
に残っているところは?という問いに対して、黒川、湯布院、別府、
指宿、という九州の代表的な温泉のほか、箱根や道後などの声も。
もちろん佐賀の温泉、古湯や嬉野、武雄も挙がっていました。
その目的は・・・、というと個別の旅館を目的としているのではなく、
観光を目的に宿泊先を選ぶ、という意見が多かったようです。


さて、今回のケースの内容は、1992年に経営者であるご主人が
亡くなったことで事業を引き継いだ奥さんが老舗旅館を切り盛りし
ていくケース。それまでは順風満帆であった旅館を続けていくべきか、
M&Aで売却すべきか、という議論からはじまり、経営革新計画の
認定を受けて大幅な施設改修を行なって新しいタイプのホテル型旅館
として再生していくなど、様々な観点から議論しました。
ホテル・旅館業界においては、需要動向の目まぐるしい変化の中で
繁閑期のバラツキやリピーター客確保の難しさ、その上装置産業型
経営やサービス人員の確保など固定費がかさばる中で、なかなか
経営革新が難しい・・・、しかも借入金も多い・・・。
これからの地方温泉旅館はどうあるべきか、熟考していきました。


今回は財務諸表の分析(損益分岐点や限界利益)や需要動向に合わ
せたマーケティングの手法、どの時点で経営を諦めるかなども、
議論の対象となりました。
佐賀でも同じような事例として、富士町の古湯や嬉野などは同じ
ような問題を抱えているかもしれません。特に地方の旅館業界に
おいては、地域協業が必要か否かなど。
本日も議論が尽きることはありませんでした。